| サイトをリニューアルしましたここをクリックしてください |
||
TIA-568-C.0 TIA-568-C.1 TIA-568-C.2 TIA-568-C.3 TIA-568-C.4 Data Centers |
TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 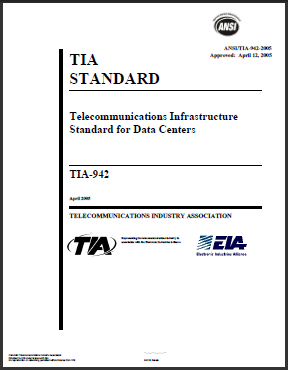 TIA(米国通信工業会)にてデータセンタ用設計規格TIA-942が2005年4月に発行されていますが、2011年秋に改定規格であるTIA-942-Aが発行される予定です。 TIA(米国通信工業会)にてデータセンタ用設計規格TIA-942が2005年4月に発行されていますが、2011年秋に改定規格であるTIA-942-Aが発行される予定です。国際標準規格としてはISO/IEC 24764 Information technology - Generic cabling systems for data centres, Edition 1.0 (2010年4月発行)があります。これはデータセンタ内の配線構成と使用されるケーブルのカテゴリーについてのみ記述されているのに対して、米国規格であるTIA-942はデータセンタの配線規格のみならず物理空間設計、電気設備設計、空調設備設計にまで言及されていることからデータセンタ構築の設計指針となる規格になっています。 * ANSI/TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers April 1, 2005 * ANSI/TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers April 12, 2005(一部訂正版) * ANSI/TIA-942-1 Addendum 1-Data Center Cabling Specifications and Application Distances March 28, 2008 (追加規格1: T1, E1, T3, E3用メディアに同軸ケーブルが追加されています。UTP使用時の距離情報にCat6Aが加わっています。) * ANSI/TIA-942-2 Addendum 2-Additional Media and Guidelines for Data Centers (追加規格2:空調環境、各TIER等内容の一部変更とCategory6Aケーブルが正式に追加されました。) 『解説』 ・本規格の意義 既存のデータセンタおよびコンピュータルーム(サーバールーム)の設計にはルーター、スイッチやストレージシステムの機器構成および電力供給と空調に重点が置かれ、建物としては床耐荷重、耐震性能そしてセキュリティ対策に焦点が当てられてきました。ケーブリングに対しては性能よりも、ユーザー見学対策として整然とした外観が重要視されていることはあまり知られていません。 さらに中規模以上のネットワーク設計にあたっては、その回線数の多さによる物理的制約から従来のケーブリング規格を適用するのには苦労が多く、場合によっては規格を外れた設計にせざるを得ない状況がありました。 規格を外れた設計にせざるを得ない場合、データセンタ毎に工夫をこらして対策を立てるのですが、皮肉にも結果として高性能を求められるデータセンタ等で使用されているケーブリングシステムの伝送性能を犠牲にし、本来の性能を発揮していないシステムの運用が行われている現状があります。(不適切なシステムトポロジー、UTPケーブルのエイリアンクロストーク、性能を低下させるプラグ付け作業等々) 規格に準拠させることが容易な一般企業の小規模なケーブリングシステム性能の方が、立派に見えるデータセンタよりも優れている場合がめずらしくありません。 その結果、データセンタ内でケーブリングに起因する問題によってネットワーク機器間の通信に異常をきたしてもその原因の特定に時間がかかるという事態が起こるのです。これはサービスを提供する側にとっても利用者にとっても大きな損失です。 これらの原因としてデータセンタの設計および施工時にケーブリングの専門家が参加していなかったり、ケーブリング担当者の知識が最新技術に対応していなかったことが考えられます。 また規格を外れた設計において、ケーブリングの伝送特性を確保するためにはメーカーの製造開発担当者レベルの知識と経験が必要となります。 そこでケーブリングメーカーと,、サービスを提供する側の通信キャリアが共同で、大規模ネットワークに対応可能な新しい設計規格を作成すればこれまでの問題は解決されることになります。 ケーブリング規格で世界をリードするTIAのTR-42内の委員会によってデータセンタの設計規格を制定した意義がここにあります。 ・規格の概要 なお、本規格はデータセンタ用ケーブリング設計規格のみならず、空調、照明、電気設備設計ならびに消火設備にまで言及しています。しかしこれは米国標準規格のため、日本での適用についてはその内容に関わる既存の各種規格や法令が存在するため、十分な注意が必要となります。 以下に規格の概要の一部を紹介します。 1.データセンタ規格の目的 序章の冒頭に『データセンタおよびコンピュータルームの設計、施工準備において考慮すべき情報を提供するものである。』とする規格の目的が述べられています。 2.適用範囲 適用される規模については、一般オフィスの小さなサーバールームからビルの複数階を占有する大型のデータセンタまでです。 また要求される信頼性もそれぞれ異なることから、設備の二重化や電源、空調のバックアップ等のレベルを4つの段階に分けて選択可能としています。なお、追加規格2 (ANSI/TIA-942-2)において空調温度や湿度そして各TIER要件の一部が修正されます。 3.データセンタケーブリングシステム ケーブリング基本構成は、既存のTIAやISOそしてJISの配線規格と同じスター型トポロジーが基本となっています。 現在一部のデータセンタや中規模コンピュータルームで採用されている物理的なスター型トポロジーと階層構造を持たない集合型パッチパネルラックによるクロスコネクト方式とは全く異なり、各接続区間のケーブリング伝送性能を考慮した設計規格となっています。 データセンタの中央部にMC=Main cross-connectを一ヶ所配置し、その周辺をMain Distribution Areaと呼び、バックボーンネットワーク機器(コアルーターやコアスイッチ)を設置します。このMCは外部回線の引込み設備やネットワーク監視室そして複数のHC=Horizontal cross-connectが接続されます。また、必要に応じてMCから直接Equipment Distribution Area内の機器との接続も行われます。 HCの周辺エリアをHorizontal Distribution Areaと呼び、ネットワーク機器、ストレージ、コンソールが収容され、HCから複数のEquipment Distribution Areaにホリゾンタルケーブルにより接続が行なわれる構造となります。 Equipment Distribution Areaaにはユーザー向けラック等が配置されて専用のアウトレットが準備されたり、近接する複数ラックをサポートするゾーンアウトレットが設置され必要なネットワーク機器が収容されます。 MC-HC間ケーブルをバックボーンケーブル、HC-アウトレット間をホリゾンタルケーブルと呼びます。また、データセンタの規模によりHCが省略される場合もあります。 4.ケーブルルート 本規格ではケーブルダクトの大きさやラック前背面の向きの統一性および電源ケーブルとデータケーブルのルートについての記述が盛込まれています。 5.電気設備と接地 日本におけるデータセンタやコンピュータルームの設計でいつも問題になるのが、電気設備と接地です。平成11年11月の電気設備技術基準解釈の一部改正により交流の場合には1,000V以下の低圧設備にIEC規格の導入が認められ、米国や欧州と同様にTN接地方式のビル構造と電気設備の工事が可能となっています。 データセンタ専用に設計されるビルは本方式を採用すべきですが、一般テナントビルの場合には建物の建築設計に依存することから、ビル完成後に入居するテナントが注文を付けるのは困難と言えます。そして、既存の多くのビルで接地にまつわるトラブルが発生または潜在している現実があります。 |
|
| To Page Top | 一部改訂 2011年8月19日 |
| HOME | NEWS | STANDARDS | SOLUTIONS | ABOUT US | CONTACT |