| サイトをリニューアルしましたここをクリックしてください |
||
TIA-568-C.0 TIA-568-C.1 TIA-568-C.2 TIA-568-C.3 TIA-568-C.4 Data Centers |
ANSI/TIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 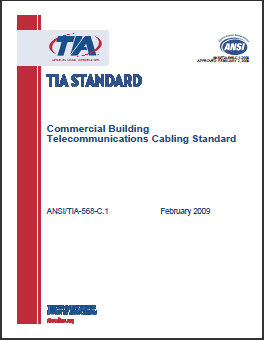 規格の目的として記述されている内容を訳を以下に紹介します。 規格の目的として記述されている内容を訳を以下に紹介します。『目的』 本規格は商用(オフィス)ビルの情報配線システムの計画と施工を可能にすることを目的とする。情報配線システムの施工はビルの建築工事中や改装中であればビルの使用後に比べて大きなコストを削減し混乱を小さくする。 本規格はあらゆる配線構成やそれぞれの(ネットワーク)要素の利用と接続のための性能と技術基準を確立している。配線システムの要求事項を決定するために、あらゆる通信サービスの性能要求が検討された。 現在は多様なサービスが利用可能で、絶え間なく新しいサービスが追加されることは望ましい性能に限界が発生する場合があることを意味している。配線システムに特定のアプリケーションが適用される時、ユーザーはアプリケーション規格、規則や機器ベンダーそして適応性、制約、補足要件についてシステムやサービス提供者を参考にすることを注意喚起される。 『解説』 TIAが定めたTIA-568-C.1規格はオフィスビルで使用されるあらゆる通信機器等をサポートするように検討されています。特にIEEEで制定される通信アプリケーション規格に関しては同じANSI(米国規格協会)配下組織であるTIA規格とは整合性が取れています。その他の一般的な通信機器についても情報配線システムで対応できない製品は殆どありません。 しかし、複数存在するケーブルカテゴリーや光ファイバーの種類等については機器側との整合性を確認する必要があり、配線設計においては事前に確認する必要があります。 ・適用範囲 本規格が適用される規模について地形的広さが3,000m、面積100万平方メートルまでのオフィススペースに5万人の利用者までとしています。 ・基本設計 旧対応規格のTIA-568-B.1と大きな差はないものの分かり易い規格となっています。 主な内容は以下のとおりです。 ・集中化された光ファイバーケーブルの配線設計 ・使用される配線ケーブルの種類 ・水平ケーブルの基本構成 (CP, MUTOAの記述を含む) 『本シリーズからの主な改定内容』 ・ケーブリングサブシステムの概念の追加 基本的にはTIA-568-C.0を踏襲しています。例え複数のビルを渡る配線システムであっても最大3階層までの設計にする必要があります。 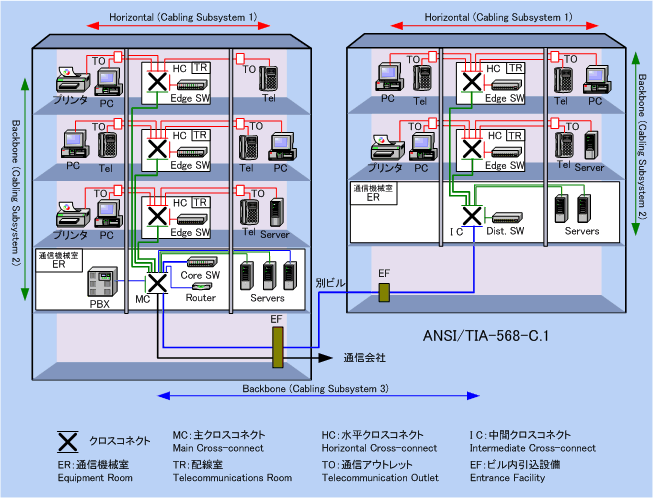 Cabling Subsystem 1 フロア内の水平配線部分を指します。 TR(配線室、通信室)から水平配線ケーブルによって接続されたTO(通信アウトレット)とワークエリア内で使用されるPCや電話機等までの配線が含まれます。 小規模のオフィスではCabling Subsystem 1だけで完結します。 Cabling Subsystem 2 TR間やフロア間を渡る幹線部分を指します。 1フロアの床面積が1,000平方メートルを超える場合や複数のフロアに渡るオフィス環境では複数のTRが配置されることになりますが、このTR間を接続する配線部分は一般的に幹線またはバックボーン配線と呼ばれています。この配線部分には水平配線とは異なる配線設計が必要となります。 Cabling Subsystem 3 複数のビル間を接続する幹線部分を指します。 学校や工場では敷地内に複数の建物が存在し、これらを接続してネットワーク化する必要があります。一般的には建物間は電気配線や通信配線のための管路が設けれられています。 この部分の通信用配線では屋外用のケーブルが使用されることになりますが、Cabling Subsystemの1から3までネットワークの速度や運用管理の観点から一貫した設計思想に基づいて設計される必要があります。 |
|
| To Page Top | 2011年8月19日 |
| HOME | NEWS | STANDARDS | SOLUTIONS | ABOUT US | CONTACT |